姫路の弁護士が 相続のお悩みを 親身になって解決します
- 姫路駅JR線南口徒歩9分
- 山陽電気鉄道本線手柄駅徒歩10分
-
来所相談30分無料
-
通話料無料
-
年中無休
-
24時間予約受付
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

来所相談30分無料
通話料無料
年中無休
24時間予約受付
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続は被相続人の持っていたお金や不動産などの財産をどうするかという問題であるため、取得する財産の多い少ないなどを巡って、相続をきっかけに相続人となる親族間で大きな争いとなってしまうことは少なくありません。
社会の変化に伴って家族の形や関係性も変化し、長寿化に伴う介護の問題も大きくなってきました。相続問題の中で取り沙汰される事情は、家族構成や被相続人との関係性、被相続人と相続人の間でなされた利益の授受や被相続人の晩年における世話・介護など、さまざまな要素が複雑に絡み合うものとなることが多いです。
それら被相続人と周りの人間の関係性などの事情と相続財産を分けるという問題が合わさり、相続争いをきっかけに、それまでは悪くなかった親族間の仲が悪くなってしまうことも少なくありません。当事者同士で話をしようとしても、血の繋がった親族・親戚であることから余計に感情的になってしまうこともあります。
弁護士が関与することで、生前から相続人間の争いの発生を抑えるための対策も含めた遺産の分け方の検討、遺言書の作成や、相続開始後の遺産分割協議など、できるだけ穏便・円満な形で解決し、相続人の間に禍根を残さないようにすることができます。

遺言書を作成することで、自身の財産をどうしたいかという自身の意思(遺志)を、遺族・相続人に伝えることができます。しかし、形式に不備があって遺言書が無効となってしまうことや、遺言の内容によって相続人間での争いを招いてしまうこともあります。遺言書の作成について弁護士に依頼することで、内容面・形式面ともに不備のない遺言書を作成し、相続に備えることができます。
また、遺産の分け方・渡し方によっては、受け取る人に大きな相続税がかかってくる可能性もあります。生前贈与なども含めて生前から準備しておくことで、死後に相続人間で大きな紛争が発生するのを防ぐことができます。
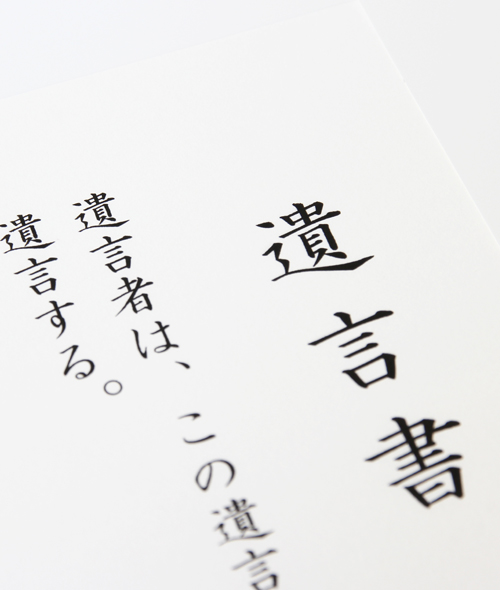
相続の準備01
遺言書を 作成したい
遺言の内容や文面については、遺言者(被相続人)の意向を実現させるにはどうすればよいか、相続人間で争いが生じるのを防ぐにはどうすればよいか、などの観点から十分に精査する必要があります。また、遺言書には法的に有効なものと認められるための形式があり、せっかく遺言書を残していても、形式面に不備があると、有効性について争いとなり、遺言が無効とされてしまうこともあります。
法的に認められる遺言の方式のうち、よく用いられるものは2つあります。「自筆証書遺言」は、遺言書の全文について遺言者が自筆していること(ただし、平成31年1月13日以降作成の遺言書については、財産目録部分についてパソコン等での作成や遺言者以外の人の作成が認められます。)、遺言者による押印があることが必要です。「公正証書遺言」は、証人2名の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公正証書の形で作成されるものです。「自筆証書遺言」については専門家である弁護士が作成に関わることにより形式的に不備の無いものを作ることができますし、「公正証書遺言」についても、公証役場・公証人との事前協議を含む手続や証人としての立会いなど、弁護士が関与すべき場合は多いです。

相続の準備02
財産が どれくらいあるか 残しておきたい
預貯金や現金のほか、不動産、株式など、相続財産にはさまざまなものが含まれます。被相続人の持っている財産について、被相続人と近しい関係にある相続人でも、全てを正確に把握しているわけではない場合は少なくありません。相続財産として何があるかを被相続人自身がまとめて残しておき、きちんと伝えられるようにしておくことで、死後に相続人らが財産の調査で苦労することや、大切な財産の存在に気付かれずに受け継がれなくなってしまうことを防ぐことができます。
また、相続人が財産を相続する場合は被相続人の債務(マイナスの財産)も相続することになりますので、借金、税金や公共料金の未納分などのマイナスの財産がある場合は、それも明らかにしなければなりません。プラスよりマイナスの財産の方が大きい場合、相続人は相続放棄や限定承認など、相続人自身がマイナスを負担しなくても済む方法をとることができ、そのための判断材料を残すことができます。
これらプラスとマイナスの財産についてまとめた財産目録を作成することで、相続税が発生するか否かやその金額も分かりますし、相続税対策として生前贈与を行った方がいいかなどについての判断材料にもなります。

相続の準備03
相続税対策を 作成したい
相続税は、相続財産の総額が一定の金額(基礎控除額)を超える場合に、相続人が支払うことになります。基礎控除額は相続人の人数によって異なり、3000万円+600万円×相続人の数、となります。たとえば相続人が1人の場合は3600万円、4人の場合は5400万円となります。各相続人が負う相続税の金額は、この基礎控除額を超えた部分の金額(課税遺産総額)を法定相続分で割り付け、相続税率を掛けたものの合計を実際の相続割合で割り付ける…という、やや複雑な計算により算出されます。大まかにいえば、控除される金額を超える部分の金額と、相続財産を各相続人が取得する割合によって、各相続人にかかる相続税が決まります。
生前贈与などをうまく活用して相続財産の総額を減らしたり、場合によっては養子縁組により法定相続人の数を増やして基礎控除額を増やしたりすることで、相続税の金額を減らすことができます。ただし、やり方を間違えると、相続税の金額が減らなかったり、脱税になってしまったりするので、専門家へ相談の上行う方がいいでしょう。
弁護士は、遺言書を作成する被相続人の意向を丁寧にうかがい、ともに考え、どのような内容にすべきか、どのような文面にすべきかを検討します。
遺言書の内容としては、相続財産の分け方、どの財産を誰に取得させたいかなどを書くことになりますが、法律上定められている財産の分け方やそれについての指定の仕方には、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、死因贈与などさまざまなものがあり、書き方によっては遺言者の意図するところと遺言書の記載の効果が異なってしまうことが起こりえます。弁護士が遺言書の作成に携わることで、遺言者の意図と文面上の表現に食い違いが生じないようにすることができます。
また、遺言書には法律上定められた形式があり、不備があると遺言書の有効性を巡る争いが生じてしまうこともあります。弁護士に依頼することにより、せっかく作成した遺言書が形式面の不備によって無効とされてしまうことを防ぐことができます。不備のない遺言書を作成するにあたって必要となる煩雑な手続についても、弁護士にお任せいただければ安心です。
01
もし遺言書がなかった 場合の遺産分割で スムーズに対応できる
02
遺言書作成を代行して もらうことができ不備のない 遺言書が作れる
03
内容に不満がある場合に 解決策や対処法を 考えてくれる
04
遺言内容による トラブルの早期解決
など
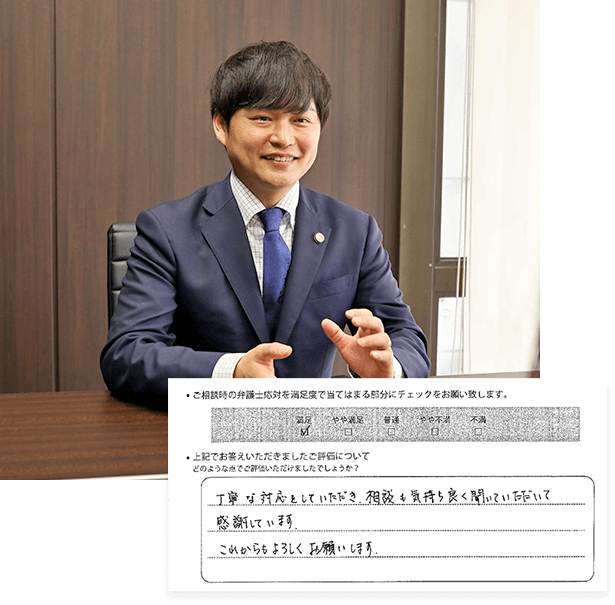
満足
丁寧な対応をしていただき、相談も気持ち良く聞いていただいて感謝しています。 これからもよろしくお願いします。
来所法律相談30分無料 相続のお悩みなら私たちにお任せください。
まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします。
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
Case01
あなたに遺産を取得させるという遺言書がある場合、遺産を受け取ることができます。また、遺言書がない場合には、各相続人が遺産を受け取るために、相続人の間で遺産分割を行う必要があります。
被相続人・相続人ともに相続についての準備や心構えがない状態で被相続人が亡くなると、相続人は突然に相続問題に直面することになります。遺産分割を行うためには、遺言書の確認、相続人調査、相続財産の調査など、有効な協議を行うために必要な手続を行う必要がありますが、何から始めたら良いか分からないのではないでしょうか。
遺産の分け方については、遺言書に記載された被相続人の意思が最優先されます。そのため、まずは相続人が遺言書を遺しているかどうか、遺言書がどのような内容になっているかを確認する必要があります。遺言書の内容によって、誰がどのような財産を受け取ることになるかが決まりますし、遺言書の形式によって検認手続の要否なども異なってきます。
遺言書が無い場合には遺産分割協議により相続人の間で遺産の分け方を決めることになりますが、遺言書が存在しないと思って遺産協議を行った後に遺言書が見つかった場合、遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議は原則として無効となってしまいます。遺産分割協議に入る前に、まずは遺言書の有無についてしっかり確認しなければなりません。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。また、遺言書に相続人以外の方に財産の何割かを与えるという内容が含まれている場合、その方(受遺者)も含めて協議を行う必要があります。
遺産分割協議の後に、協議に参加した相続人以外にも相続人が存在するということが判明した場合、遺産分割協議が無効になってしまう可能性があります。そうならないためには、遺産分割協議に入る前に相続人の全員について明らかにし、相続人全員で協議を行わなければなりません。
相続人の全員について明らかにするためには、被相続人の戸籍を取得することにより親族関係を確認する必要があります。近しい親族も知らない被相続人の子などの相続人が存在する場合もあります。また、相続権の順位(被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹)や、相続人の一部が被相続人より前に死亡している場合の代襲相続などの問題もあり、相続人の範囲については専門家でなければ正確に把握できないことも多いです。
そのため、相続人の調査について、専門家である弁護士に相談する方が良い場合も多いでしょう。
相続人が被相続人と近しい関係にあっても、被相続人の持っている財産の全てについて把握しているとは限りません。また、被相続人が自身の財産について把握しきれていない場合もあります。遺言書に「この財産は誰々に」と記載されていればその財産はその通りに相続されることとなりますが、遺言書に記載されていない財産がある場合、その財産の相続については遺産分割協議で決める必要があります。
そのため、被相続人名義の財産について網羅的に調査する必要があります。預金通帳や金融機関からの郵便物、固定資産税納税通知書などから、どの金融機関に口座を所有しているか、どこの市町村に不動産を所有しているかなどを把握し、不動産の名寄帳や銀行の残高照会書、取引履歴などを取得することで、遺産の金額・価値を知ることができます。
また、プラスの財産だけでなく、借金や公共料金の未納などのマイナスの財産についても調査する必要があります。
Case02
被相続人が遺言書を遺しており、財産の分け方について言及されている場合、遺言書に記載されている被相続人の意思は、法律上定められている財産の分け方(法定相続分)や相続人間での協議による決定に優先します。
「この財産についてはこの人に取得させる」という内容の遺言があれば、その財産については指定された人(受遺者)が受け取ることになりますが、相続人及び受遺者全員の合意があれば、その財産について遺言書の内容と異なる分け方をすることができます。また、遺言書がある場合でも、「誰が何割」というような相続の割合が指定されている場合や、遺言書で言及されていない財産がある場合は、遺産分割協議を行う必要があります。
検認とは、裁判所で行われる遺言書の確認手続です。相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、また、遺言書の偽造や改ざんを防ぐために、遺言書の状態や記載内容を確認して記録する手続です。被相続人(遺言者)の生前から遺言書を保管している相続人、あるいは被相続人の死後に遺品の整理などをしていて遺言書を発見した相続人は、遅滞なく裁判所に検認手続を請求する必要があります。 自筆証書遺言や秘密証書遺言については、裁判所での検認が必要です。一方、公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管され、改ざんのおそれがないことが担保されていることから、裁判所での検認は不要となります。なお、法改正により令和2年7月10日以降は自筆証書遺言について遺言者本人が法務局で申請することで、法務局にて遺言書を保管してもらうことができるようになり、その場合、検認は不要となります。
また、封印されている遺言書の場合、検認手続の前に遺言書を開封してはいけません。検認前に開封してしまったからといって遺言書が無効になることはありませんが、5万円以下の過料が課せられる可能性がありますし、他の相続人から「検認の前に発見者が改ざんした可能性がある」という疑いをかけられるなど、トラブルの原因になる場合があるためです。
遺言執行者とは、文字通り遺言を執行する人、亡くなった遺言者に代わって、遺言者が託した遺言の内容を実現する役目を負う人です。相続財産の調査や目録の作成、預貯金の引き下ろし、不動産の名義変更の登記手続きなど、相続に関するあらゆる業務を行います。
多くの場合、遺言の執行にあたって遺言執行者の存在は必須ではなく、相続人のうちの誰かが上記の手続を自主的に行うことになることも多いでしょうが、遺言の執行について責任を負うことが明確な遺言執行者がいた方が、円滑かつ確実な遺言の実現につながります。また、遺言の内容によってはその実現のために遺言執行者が必須である場合もあります。
遺言執行者は、遺言書で指定することができますが、遺言者の死亡後(相続開始後)に家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうこともできます。相続人が遺言執行者となることもあれば、弁護士などの専門家が選任されることもあります。
Case03
遺言書がない場合や、遺言書の記載だけでは遺産の分け方が決まりきらない場合、相続人間で遺産の分け方を決める、遺産分割協議を行うこととなります。
一部の相続人が他の相続人に黙って遺産を独占することは許されませんし、金融機関での預貯金の解約や法務局での不動産の名義変更の登記手続にあたっては、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書が必要となります。令和元年7月1日より、預貯金のうち一定額については遺産分割協議前に払戻しが受けられるようになりましたが、あくまで葬儀費用や相続人の生活費などのために取り急ぎ一部の払戻しを受けることができるに過ぎず、遺産全体を分割して各相続人が取得するためには、遺産分割協議を経ることが必要です。遺産分割協議は、相続人が適正な手続に則って遺産を受け取るために必要な手続なのです。
民法には法定の相続分(被相続人との関係に応じた、遺産の受取りの割合)が定められています。遺産分割協議にあたって、相続人たちは法定相続人に従った分割をすることもできますし、法定相続分に拘束されることなく、自分たちが決めた分け方で遺産を分割することもできます。
また、相続財産を受け取りたくない相続人がいる場合、後述の相続放棄のほか、その相続人の相続分をゼロとする合意をしたり、その相続人が被相続人の生前に十分な利益を受けた旨を書面で表明したりすることで、遺産を受け取らないようにすることもできます(事実上の相続放棄)。
遺産分割協議の結果を遺産分割協議書という合意書にして相続人全員が署名押印することで、適法な遺産分割協議が行われたということと、協議の結果、被相続人の財産をこのように分けることが決まった、という内容を示すことができ、預貯金の解約や不動産の登記などの遺産の処分が可能となります。
Case04
相続人であっても、被相続人の財産を受け取りたくないという場合もあります。被相続人に負債があり、そちらの方がプラスの財産よりも多い場合や、生前の相続人との関係が良くなかったなどの理由から、心情として財産の金額やプラスマイナスにかかわらず受取りを辞退したいような場合です。
このような場合、遺言書や遺産分割協議に従って相続財産を受け取るのではなく、相続放棄や限定承認といった方法を取ることができます。
前述(→遺産分割協議)の「事実上の相続放棄」により相続財産の受取りを辞退することもできますが、この方法ではマイナスの財産を受け継ぐことを免れることは出来ないため、注意が必要です。
自分が負っている負債について伝えることへの心理的抵抗から、被相続人の負債については、プラスの財産以上に相続人に知らされていないことが多いです。被相続人の死後に支払督促の通知書や債権者からの連絡などにより負債の存在が発覚することも少なくありません。
相続により、相続人は被相続人の財産だけでなく、負債も受け継ぐことになります。そのため、プラスの財産よりも負債の方が大きい場合、相続人は身銭を切って被相続人の負債を支払うことになりますが、相続放棄や限定承認といった方法により、身銭を切って被相続人の負債を支払わなくてもよくなります。
被相続人が負債を残して亡くなった場合、債権者から相続人に連絡が来ることがあります。相続放棄するのであれば連絡に応じる必要はありませんが、相続放棄を検討している、あるいは相続放棄した旨を説明することで、債権者が繰り返し連絡してくるのを止めることができます。
債権者から、相続放棄手続きの完了により発行される証明書(相続放棄申述受理通知書)を渡してほしいと言われることがありますが、そのような場合には証明書のコピーまたは原本を渡します。
通常は相続放棄する旨を伝えることで債権者からの頻繁な連絡は止みますが、それでも頻繁に連絡してくる債権者もいます。弁護士に相続放棄などの手続を依頼することで、そうした熱心な債権者からの連絡への対応も弁護士に任せることができ、不安やストレスから解放されます。
相続人間で遺産分割協議を行っても、話合いがまとまらなかったり、取り分の少ない相続人が遺留分減殺請求または遺留分侵害額請求を行ったりということもありますし、不動産の相続については預貯金や現金などの分割しやすい財産よりも争いになる場合が多いです。相続人への生前贈与があったか否かや、被相続人への貢献(寄与分)といった話が出てくることもありますが、こうした事情について法的に認められるものか否かは、専門家でなければ判断することが難しいですし、裁判所の判断を仰ぐべき場合もあります。

遺産分割協議では多くの場合、親族間でのお金の争いとなります。親きょうだいや親戚間での争いであるがためになお一層感情的になってしまい、話がまとまらなくなってしまうことも少なくありません。
また、被相続人の生前に家業を手伝っていた、亡くなる前に世話をしていた・介護にあたっていた、 多額の財産を受け取っていたなど、さまざまな事情が主張されることがあります。こうした事情が法的に各相続人の取り分を加減すべき事情にあたるか否かについては、専門家でなければ判断が難しいことが多く、弁護士に相談したり、調停・審判といった裁判所での手続に移行したりすべき場合が多いでしょう。

被相続人による遺産の分け方の指定によって、一定の範囲の相続人(遺留分権利者)が民法に定められた最低限の取り分(遺留分)に満たない財産しか受け取れない(あるいは全く受け取れない)こととされた場合、遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をすることができます。この請求により、遺留分権利者は、自身の遺留分が侵害されている分の金額について、金銭の支払を受けることができます。遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年が経過するとできなくなってしまいますので、注意が必要です。
また、令和元年7月1日の改正民法施行より前に開始した相続については、遺留分侵害額請求ではなく、改正前民法に定められていた「遺留分減殺請求」により、遺留分を侵害する形で贈与、遺贈などされたものの返還を請求することができます。

被相続人の生前に被相続人から財産の贈与を受けた相続人がいる場合、その内容によっては、贈与を受けたことを考慮して遺産分割を行うべきことがあります。これを、「特別受益の持戻し」といいます。
結婚の際の持参金・結納金、居住用の不動産の贈与や、多額の生活費の援助などについては、特別受益にあたる可能性があります。
特別受益が存在する場合、相続開始時の財産に特別受益の金額を加算したものが分割すべき財産の合計額となり、特別受益を得ている相続人については、その特別受益分を差し引いた残額を相続財産として得ることになります。

被相続人の事業について(無償で)一緒に働いたり、被相続人のためにお金を出したりして、被相続人の財産の維持や増加に貢献(寄与)した相続人については、遺産分割の際にその貢献が考慮されることがあります(寄与分)。寄与分がある場合、相続開始時の財産から寄与分にあたる金額を差し引いたものが分割すべき財産の金額となり、寄与分が認められる相続人については、寄与分を加えたものを相続財産として得ることになります。
よく問題となるのが、被相続人の病気の際や老後に看護を行った親族がいる場合です。親族は互いに生活上助け合うべきものとされていることから、こうした被相続人の看護について寄与分が認められるには、親族として一般的に期待される以上のものであること、それにより看護費用の支出が避けられ、被相続人の財産の維持・増加に貢献したと言える場合であることが必要です。
また、相続人ではない親族(被相続人の子の配偶者など)が被相続人の看護などを行い、財産の維持・増加に貢献した場合について、以前は寄与分などの権利は認められていませんでしたが、法改正により、被相続人の財産を相続した相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。

建物や土地といった不動産の相続については4つの方法があります。
1つ目は、複数の相続人の共有とすることですが、不動産を利用することを考えると、共有ではなく、1つの不動産につき1人の相続人が取得することが望ましい場合も多いです。 p
2つ目の方法は現物分割です。1人の相続人が不動産を相続する(その分、他の相続人は他の財産を取得するなどする)、あるいは土地を分筆して複数の相続人がそれぞれの土地を取得するというように、不動産の現物を1人が取得、または複数人の相続人が分割して取得する方法です。
3つ目の方法は代償分割で、1人の相続人が不動産を相続し、他の相続人に代償の金銭を支払うというものです。
4つ目の方法は換価分割といい、不動産を第三者に売って、その代金を相続人間で分割する換価分割という方法です。
不動産の相続については、各相続人の不動産の取得に対する希望や折衝の可能性を考慮して、いずれの方法が適切かを検討することとなります。
一口に相続といっても、相続人の置かれた状況により、進むべき方向はさまざまです。相続放棄を検討すべき場合もありますし、遺産分割協議でかなり揉めてしまうこともあります。遺言書があるからといって全てが滞りなく決まってしまうケースばかりではなく、様々な問題が出てくるケースも少なくありません。また、過去の相続に遡って解決しなければならない場合や、当事者間での話合いではなく、調停や訴訟などの裁判所での手続による方がよい場合もあります。
弁護士は、遺言書による相続、遺産分割協議、相続放棄といった相続におけるあらゆる問題について対応できます。弁護士に依頼することで、最適な解決とそれに向けた最適な方法・手段を検討し、お手伝いさせていただきます。

CASE01
相続財産として何があるのか分からない、誰が相続人にあたるのか分からない、遺言書がなくどのように遺産を分けるべきか分からない、など、相続について分からないことだらけであることが多いと思います。
また、被相続人の死亡以前に発生した別の相続について遺産分割協議が行われておらず、不動産の登記が数代前の所有者のままといったケースも多く見受けられます。このような場合、世代をまたぐ多数の相続人間で協議をしなければならないことが多く、また、遺産分割協議書の内容も登記のために適切な形にしなければなりません。
いざ相続をしようとしても、どのように進めて良いか分からない場合、弁護士にご相談いただければ、何をどういった順番で進めていかなければならないかというアドバイスやサポートから、代理人としての協議・交渉、遺産分割協議書などの書面の作成まで、あらゆる場面で力になることができます。
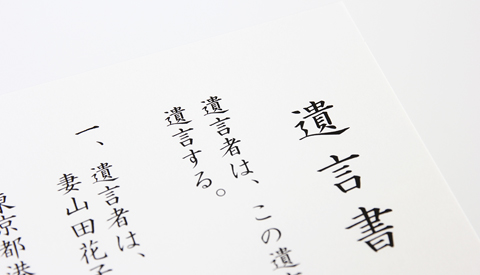
CASE02
遺言書がある場合、基本的には遺言書の記載内容に沿って遺産を分割することとなりますが、裁判所での遺言書の検認など、しかるべき手続きをとりながら進めていく必要があります。
また、遺産の分割の仕方については遺言書に書かれている被相続人の意向が優先されますが、遺留分や寄与分の問題が出てくる場合や、遺言に書かれていない財産がある場合、また、遺言書作成時と相続開始時とで、相続人や財産の有無等の状況が変化している場合もあります。遺言書の内容の解釈が問題となる場合もあります。
また、遺言書の内容が実現されると不利になる相続人から、遺言書の有効性が争われることもあります。押印や日付がないといった形式面での不備や、遺言書は被相続人以外の人間が偽造したものであるとか、遺言書を作成した時点で被相続人は認知症が進んでおり、遺言を作成するに足る能力(遺言能力)がある状態で書かれたものではないなどの理由が主張されます。
遺言の有効性について相続人間の話合いでは解決できない場合、遺言無効確認の調停や訴訟で決着を付けることとなります。

CASE03
相続放棄を行えば、被相続人のプラスの財産を受け取ることができなくなる代わりに、被相続人の負債を負うことがなくなります。
また、相続人から受け継ぐプラスの財産の限度で負債を受け継ぐ(つまり、相続人が身銭を切ることはなくなる)、限定承認という方法もあります。
相続放棄前に遺産の処分などを行うと、被相続人の債務を含め相続することを承認した(単純承認)とみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなる可能性がありますので、相続放棄や限定承認を選択する可能性がある場合には、被相続人の財産や身の回りのものの処分について、特に慎重になる必要があります。
相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内にしなければならないという制限がありますが、裁判所への申請により、相続放棄するか否かを検討する期間(熟慮期間)を伸ばすことができます。
また、期間を過ぎてしまっている場合でも、債務を含めた相続財産の全容については知りえず、また知りえなかったことについて相当な理由があると認められ、相続財産の内容を知ってから3か月が経過する前であれば、相続放棄や熟慮期間の伸長ができる場合がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

CASE04
遺産分割協議について、遺産の範囲や分け方について特に争いもなく、スムーズに終了、という場合ばかりではありません。「遺産はこれで全部だ」「いやほかにもあるだろう」という遺産の範囲の争いや、「被相続人との生前の関係からすると自分はもっと多くもらうべきだ」というような取り分の話、「あなたは昔、被相続人からお金をもらっただろう」というような特別受益の話など、さまざまな話が出てきて収集が付かなくなることも多いです。
当事者間の話合いでは解決できない場合、専門家である弁護士の介入によって法的な妥当性を示しながら協議・交渉することにより解決の道が見えてきます。また、揉めている遺産分割協議の場合、その結果についてまとめる遺産分割協議書の作成にあたっては、紛争の蒸し返しなどが起こらないよう、内容には特に気を付けなければなりません。
当事者間の話合いでは解決が難しくとも、遺産分割調停という裁判所での話合いにより解決できる場合もありますし、話合いではどうしても解決できないという場合には、審判という裁判所の判断で分割することになります。遺産分割協議でもめてしまったら、弁護士を代理人とする交渉や、調停・審判といった裁判所での手続により解決を目指すことを検討すべきです。
01
お問い合わせ
02
ご予約
03
来所相談
04
ご契約
05
解決
来所法律相談30分無料 相続のお悩みなら私たちにお任せください。
まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします。
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
裁判例 01
遺言書作成当時に遺言者が認知症や痴呆の症状を発症していたことを理由として遺言能力の有無が争われることは少なくありません。
この点について争われた裁判例として、遺言者に軽度の認知症があっても、遺言作成時に自ら遺産の分け方やその理由について述べていたことや、周囲の人間との会話がしっかりと成立していたことを理由に遺言を有効とした裁判例があります(平成6年1月21日和歌山地裁、平成14年3月25日東京高裁等)。
一方で、公証人など他人が読み上げた内容や質問にうなずいたり「はい」などの答えをしたりしたのみでは遺言能力があったとは認められないとされた裁判例があります(昭和51年1月16日最高裁、平成18年9月15日横浜地裁)。
それぞれの裁判例は、上に上げた事情のみではなくその他の諸々の事情から遺言能力の有無を判断したものですが、遺言者の言動から、遺言の内容を理解したり、自ら考えたりする能力の有無を判断しているものといえます。認知症であっても遺言能力があると認められる場合もあれば、遺言能力がないと判断されてしまう場合もあるため、高齢で今後の意思能力の低下の不安がある方は早めに遺言書を作成することが望ましいといえます。また、すでに認知症を発症している方が遺言書を作成する場合は、後に遺言能力の有無について争われた場合に備え、認知機能についての診断書など、遺言能力があったと示すための証拠を残しておくとよいでしょう。
裁判例 02
遺留分減殺請求権の行使には、権利行使が可能になった時(相続の開始と減殺すべき贈与か遺贈があったことを知った時)から1年、相続の開始から10年という時間制限があり、その期限内に遺留分減殺の意思表示があったか否かという争いになることがあります。
そのため、遺留分減殺請求権については、消滅時効の起算点(いつから数えて1年とすべきか)や、期限内になされた遺留分権利者の行為が遺留分減殺請求の意思表示にあたるか否かなどが裁判上で問題となります。
ある裁判例では、特定の相続人に不動産の全部を相続させるという、他の相続人(遺留分権利者)の遺留分を侵害することが明らかな内容の遺言書がある場合に、その遺留分権利者が自身の取り分があることを主張して遺産分割協議書に押印しなかったことが、遺留分減殺請求の意思表示にあたるとされました(昭和60年4月30日京都地裁)。
一方、遺産分割協議や遺産分割調停の申立てに遺留分減殺請求の意思表示が含まれるか否かについては、当然にそのような意思表示が含まれるものではない(個別具体的な事情によっては含まれる場合もある)という規範を示した上、その事件の具体的な事情からは、遺留分権利者による遺産分割協議や遺産分割調停の申立てといった行為に遺留分減殺請求の意思表示が含まれていたとはいえないとした裁判例があります(平成4年7月20日東京高裁)。
これらの裁判例からいえることは、遺留分権利者が自身の取り分を主張するような言動に出たとしても、それが遺留分減殺請求の意思表示にあたると認められるとは限らないため、遺留分の権利を行使する意思があるならば、そのような意思表示を時効が来る前に行ったということが後で確認できるよう、日付入りの書面で行った方がよいということです。

生前から相続の対策を始めるにあたっては、「今はまだ元気だし、もう少し先でも大丈夫だろう」とお考えかもしれません。また、周りのご家族などからも、「今のうちに相続について考えておいたら?」というような話は切り出しにくいところもあると思います。
しかし、元気であるうちにこそ、相続の対策を始めなければなりません。遺言書の作成や相続税対策などについて弁護士にお任せいただくとしても、自分の財産をどのように分けるかなどについて考えることはエネルギーの要ることであり、元気のあるうちに行うべきです。また、相続人のどなたかに介護や身の回りの世話などをしてもらう代わりに財産を与えることを約束するなど、単に自分の死後のことについて決めるだけでなく、自分の現在から死亡までという将来のことも含めて検討することができます。このような点からも、相続のことについて早めに検討されるべきといえます。
被相続人が亡くなって相続人となった方からのご相談についても、弁護士に相談するのは当事者間で話し合ってみてうまくいかなかったときでいいかな、と思われるかもしれませんが、早めにご相談いただくことで、紛争が大きくなる前に最善の方針・方策について検討することができます。 どうかお早めにご相談いただければと思います。


姫路周辺地域では、東京や大阪などに比べ自宅土地建物や田畑、山林などの不動産を所有している方の割合が多く、相続においては複数の相続人の間で不動産を含む遺産をどう分けるかが問題になることが多いという傾向があります。
不動産の相続については、相続人間の共有や分割といった方法もあるものの、誰か1人の相続人が取得するという分け方になることが多く、他の相続人が取得する預貯金等の遺産が無かったり、不動産を取得する相続人が他の相続人に不動産取得の代償として支払う金銭を持っていなかったりする場合、各相続人が取得する財産の価値・価額に不公平が生じ、揉めてしまうことになります。これは、遺言書がない場合の遺産分割協議でも問題になりますし、遺言書がある場合にも遺留分侵害額請求などの形で取り分の少ない相続人からの主張がなされたりします。
また、不動産については、被相続人の先代の相続について遺産分割協議や相続に伴う登記が行われていない、という事例も少なからず見受けられます。このような場合、今後のトラブルを防ぐためにも相続に伴う登記手続をきちんと行った方がよく、そのためには対象となる不動産の相続人間で協議した上、適切な形で遺産分割協議書を作成することが必要です。 相続に関する紛争を予防するために相続の準備をされたい方としては、財産の分け方について「この人に多く取得させたい」というようなご自分の意思を反映しつつ、相続人たちが争うことになる可能性ができるだけ低くなるような内容を考える必要があります。
また、遺産を相続することになった方は、相続人の1人として、他の相続人とともに遺産分割協議や遺産の管理、処分などにあたることとなりますが、被相続人と各相続人を取り巻く事情を踏まえた公正な解決を図るために、専門家による法的主張や裁判所での手続が必要な場合も少なくありません。 相続は、どなたでも身近に起こりうることでありながら、解決にあたっては一般の方に馴染みのない法律的な諸問題と直面することになります。専門家である弁護士にご相談いただければ、最善の解決に向けて尽力いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※30分以降は、30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談となります。
※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
※当日、当法人にご依頼いただきました場合、延長された法律相談は無料とさせていただきます。
延長をご希望された場合でも他のご予約の関係で対応できないケースもございますのでご了承下さいませ。